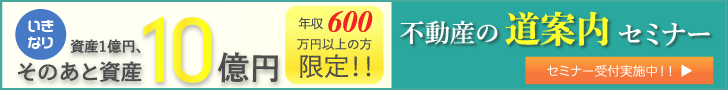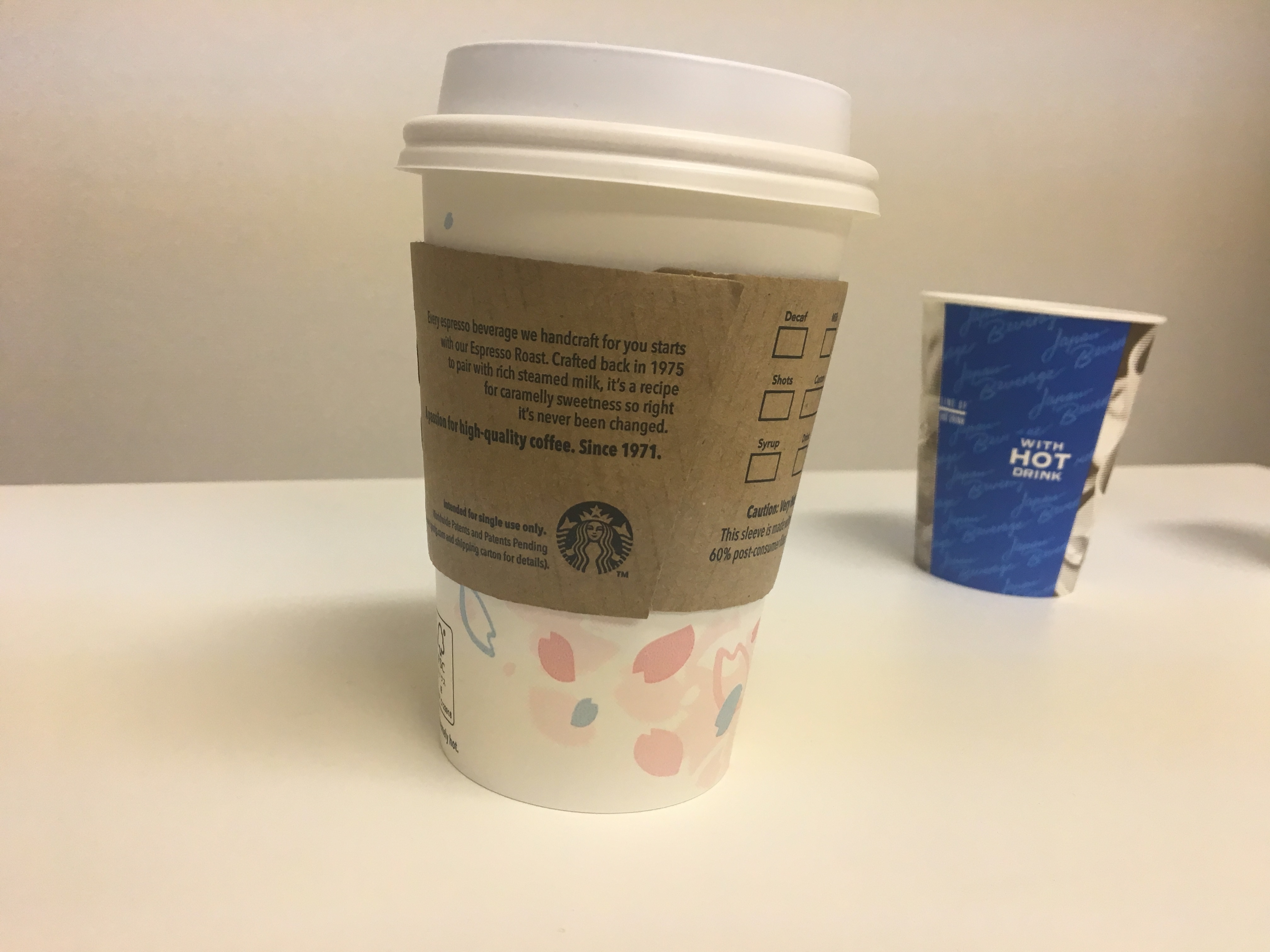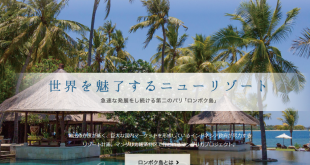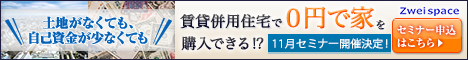海外不動産事情にお詳しい、 NEXT GROUP 代表 で、PT LOMBOK NEXT PARTNERS 代表取締役の 中邨 宏季 社長に、おききします。
Read More »不動産投資戦略 その1
不動産投資戦略の立案 会社員や事業経営の傍ら不動産投資で不労所得をあげたいのであればその目的に沿った戦略を立てることが必要です。 投資家自身が自分の戦略を明確に説明できないことが多いのが多いのです。自分が何を目指して投資をしているのかを忘れてしまうと、自分が本来買うべきでない物件に魅力を感じてしまいます。実際に自分が貯めた資金を投資する場に身を置いて、それを自分のこととして判断する状況にならないと投資戦略に一本の軸を据えることの重要性を理解することはできません。数億円以上の投資規模になっているのであれば専門家の知識の利用も検討するのも必要です。 当初の戦略立案にしっかり時間を使うことが重要です。どのような地域でどんな物件を購入するのか、融資はどこを使うのか、何が妥協出来て何が絶対に譲れない条件なのかを考慮する必要があります。 投資戦略を立てる上で考えるべきポイントは、銀行はどこを使うべきか。探すべき物件の地域、構造、収益性はどのようなものか等、設定した条件に基づいて物件を探すことになるが、実際はいくら探してもその条件で物件が見つからないことが多くあります。 その原因は専門家が足りないか情報が足りないかのどちらかです。戦略に沿った行動になっているのかを随時自分でチェックし必要に応じて戦略そのものを修正しなければなりません。 不動産投資には新築投資、築古アパート投資、大規模RC投資など様々な手法がありますが、情報を収集しどんな投資法が自分に合っているか検討する必要があります。自分の立てた投資戦略についてなせ株式やFXや他の投資でないかを明確に語れるようになれる必要があります。 何故大きな金額を投資するべきだというかと言うとそれは投資家目線だけでなく経営者の視点から見てもそう言っているからです。 経営者は多くの融資を銀行から受けながら、利益率が低いくても大きな市場を持つ分野に資金を投入してビジネスを行っています。そうでないと、大きな額の利益を残すことは出来ないからです。 売上は基本的に投資規模に比例して上がることになりますが、利益率は売り上げの大小によって変化しないからです。売上1億の街の飲食店も、売り上げ100億円のチェーン店も飲食店も飲食店という業態であれば利益率は大して変わらない場合も多いのです。 あくまで利益率のみに焦点を当てた例になりますが、これを不動産投資に置き換えると1億円の物件を一つ所有するには物件を探し・銀行から融資承諾・売主と契約・決済を行う必要があります。 1億円の物件を1棟所有するのも10棟所有するのも1つずつのプロセスは変わらないのです。基本的には一つの物件について、物件を探しから決済するという変わりない過程を経ることになります。これは不動産の市場規模がとてつもなく大きいから、再現性を伴って何度も実現できるのです。 もちろん物件をいくつも買うのは容易ではなりません。ただ市場自体があるかどうかわからない分野で、革新的で利益率の高いビジネスモデルを考え出すよりもはるかに再現性があり現実的なのです。 市場にはマーケットサイズというものがあり、各業界はそのマーケットサイズの中で凌ぎを削っているのです。不動産売買は、日本国内だけでも何十兆円もの市場があります。一人が数億円程度買ったところで、市場が枯渇したり、ビジネスのルールが変わることはまずないのです。 (酒本 経営戦略塾) ……………………………………………………………………… 酒本氏のセミナーに参加されたい方は、以下のフォームでお申込みください! セミナー選択必須 2月9日(19時〜):賃貸併用 丸の内 JPタワー2月12日(13時~):渋谷 クォーツギャラリー渋谷2月22日(19時〜):賃貸併用 丸の内 JPタワー2月25日(13時~):渋谷 クォーツギャラリー渋谷3月12日(13時~):渋谷 クォーツギャラリー渋谷3月25日(13時~):渋谷 クォーツギャラリー渋谷個別面談予約する(折り返しで時間指定、場所:麹町オフィス) 姓必須 名必須 電話番号必須 メール必須 業界 -なし-通信業技術系企業政府/地方公共団体製造業金融サービス業IT サービス業教育機関医薬品業不動産業コンサルタント業医療機関 年収 -なし-600万以上800万以上1000万以上1500万以上2000万以上
Read More »不動産投資戦略 その5
1棟目を買うのは東京圏にする 人口減少社会において人口が増加している地域は47都道府県のうち、一極集中の東京、福岡、愛知、神奈川になります。東京の人口増は東京オリンピックの開催決定により、東京のインフラ整備が進み不動産価格が急騰しております。埼玉・千葉は地域により考察が必要です。埼玉は大宮より都心近隣、千葉は千葉市より都心近隣。大阪は以外にも人口減少傾向にあります。 一極集中は年々加速して東京・埼玉(大宮より都心近隣)・神奈川・千葉(千葉市より都心近隣)のいわゆる東京圏といわれる地域は、人口流入数が昨年対比で1万2884人増の年間10万9408人が流入して年々増加しております。さらにこの地域の特徴は大学や企業などが沢山あり単身者が多い事も特徴としてあげられます。労働者人口が毎年10万人都心に流入するという事は、計算上単身者向け住宅が毎年10万個必要となる計算です。 東京都心においては仕事を求めての注入が多い事により、ファミリータイプより単身者タイプの東京圏の需要が増えるのが予想されます。東京圏入居者の単身者は中堅層以下が多く、車の所有率が低い為に駅から徒歩圏内の物件を選ぶ事が重要になります。市場規模でいうと2010年に1.9兆円規模の単身者需要の希望が2030年に2.1兆円と2000億円規模で増えると予想されております。 1棟10室の部屋があったとすると10万÷10室=1万個需要がでます。つまりインカムゲインには需要増で空室リスクは低く、キャピタルゲインにおいては、東京オリンピックのインフラ整備における土地の高騰により売却増が狙えるのです。なぜ東京圏の土地が上がっているかというとREIT(不動産投資信託)つまり海外の投資マネーが大量に国内に流れ込んでいるからです。 REITという仕組みは米国が発祥でReal Estate Investment Trustの略でREITと呼ばれています。投資家から集めた資金で不動産などを購入し、その売却益や家賃収入を投資家に分配する金融商品です。従来の投資信託は主に有価証券を対象としてましたが、2000年11月に施行された改正証券投資信託法により不動産等も運用対象とすることが可能になりました。株式と同じように株式市場で売買されています。東京証券取引所は2001年にREITの売買市場を立ち上げました。 このREITの数字は毎年増加しております。理由としては円安傾向があり日本の不動産が買いやすい状況にある為にREITの数字が上がっているのです。中国最大の不動産会社「緑地集団」もみずほと提携して日本の不動産を買収して行くと発表しております。 ではオリンピック以降のその後はどうなるか、事例を検証してみるとロンドンオリンピック、北京オリンピックのその後も両方とも不動産は上昇しております。つまりインフラ整備が行われる事により、一極人口流入の流れが進みオリンピック以降もその傾向は続くと考えられます。 また中国ビザの中国政府の政策緩和により中国人の来日の増加が毎年起こっており、それも一つの要因として単身者タイプの不動産需要増が予想されます。2015年1月から中国人に対するビザの発給要件がさらに緩和され、具体的には有効期間中は何度でも日本に入国できる数次ビザの発給要件が緩和され、これまで求めていた日本への渡航歴要件の廃止や日本側身元保証人からの身元保証書等の書類要件が省略されました。皆さんも街中で中国人を見る機会が多くなったと思います。外国人を対象にしたホテル等も需要増となる事が予想されます。 この様に1棟目を買うのは戦略と戦術が必要でありこの様な必須不可欠な知識を皆さんと一緒に勉強して行きましょう。 (酒本 経営戦略塾)
Read More »不動産投資戦略 その4
不動産投資戦略 その4 劣化対策等級を取得してキャッシュフローを良くする。 皆さんが車をローンで買う際に一括払い、12回払い、24回払い、36回払い、48回払い、60回払い、72回払いでは当然毎月の支払いも変わって来ます。これと同様に不動産を購入した際に何年で支払うかという融資期間がキャッシュフローを生む大きな要素となります。 そこで今回は劣化対策等数について学んでいきましょう。不動産が長持ちするということは不動産の価値が高いというのは単純に理解できると思います。しかし経済的な優遇を得られるようには見えません。しかしこの劣化対策等級を取得していると、銀行側に劇的に資産価値評価額を上げることができ、経済的優遇が得られるのです。 劣化対策等級というのは1~3までの3段階あり等級1は建築基準法を守っていれば取れる一番低いレベル、劣化対策等級3が最も高いレベルです。劣化対策等級が1つ上がれば25~30年の耐久期間が伸びるとされ、等級2なら50~60年、等級3なら75~90年は建物を使い続けることができるレベルということです。 投資対象を7000万程度の賃貸併用住宅とした場合、銀行は通常の耐用年数は22年としていますが、劣化対策等級2級以上を取得していると、耐用年数30年として融資期間を策定してくれるのです。 インカムゲインつまり家賃収入では、12年と20年ではその期間の違いの分だけ毎月の融資の返済額が変わりますから、キャッシュフローが出やすくなって投資物件としての収入が大きく上がることになります。短年で融資返済期間を組むと家賃収入に対して融資の返済額の割合が大きく、キャッシュフローが出にくいですが、融資返済期間が伸びることで毎月の手残り金額が数倍違うという場合もあります。車のローンの返済年数による毎月の返済額と同様な計算です。 キャピタルゲインの方でも考えてみましょう。つまり不動産の売却を10年でしたとして、その資産価値をどのように査定するのかを計算してみましょう。 不動産、今回は賃貸併用住宅を7000万円で建築したとすると、劣化対策等級を取らない状態では22年で価値ゼロに向けて資産価値が落ちていく計算になります。10年経つと22年ではあと12年持つという計算ですから、築10年では7000万円÷22年×12年=3818万円になります。 ところが劣化対策等級を取っていれば同様に計算すると、10年経つと30年ではあと20年持つという計算ですから、築10年では7000万円÷30年×20年=4666万円となります。その差は約848万円にもなります。銀行の査定評価が大きく変わることで売却した時に結果的に高値で売却できることになるのです。 もし劣化対策等級を取らなくても融資の下りやすい地方銀行等により、安易に30年間の銀行融資が受けられた場合でも、売却のタイミングが来た際に銀行の査定額が変わってくるのです。劣化対策等級は施工段階と完成後の検査機関の検査後に、住宅性能評価書を交付されます。新築する時にしか取得できません。これから賃貸併用住宅を建てたいと考えている人は、必ず劣化対策等級2級以上を取得することを忘れないようにするのが賢明です。 (酒本 経営戦略塾)
Read More »不動産投資戦略 その3
不動産投資戦略 その3 不動産投資では銀行融資を受けて物件にレバレッジをかけて購入するのは前回説明しました。しかしオーナーが途中で亡くなってしまった場合はこの銀行への返済はどうなるのでしょうか? そのような事態に備えてのリスクヘッジで団体信用生命保険と呼ばれる制度があります。団体信用生命保険は団信と一般的によばれており、オーナーが返済中に亡くなった場合にオーナーの代わりに生命保険会社が銀行融資返済を肩代わりして貰う制度です。マイホームの銀行融資は、団体信用生命保険へ加入が原則として義務づけられています。しかし不動産投資ローンの場合は自動加入ではなく自分で別途加入手続きを行う必要があります。 団体信用生命保険は団信と書かれる様に団体で加入する保険です。個別に生命保険会社と契約するのではなく、銀行が生命保険会社に一括で申し込みます。銀行と契約した人全員が加入するので保険料が安くなる為です。一般的な保険と違い加入時の年齢に比例して保険料が上がるわけでもありません。20代でも50代でも同じ保険料で加入できるのです。この保険に入っていればオーナーが亡くなっても銀行返済が一括返済されるので、残された家族は借入残高がない状態で賃貸物件を相続できます。 これも不動産投資の大きな利点です。生命保険代わりに家族に資産を残せるのです。結婚を機に20代・30代で不動産投資を始めるのは家族の為を思って、オーナーが亡くなった万が一に負債が無く家族に不動産を相続できるのです。オーナーが亡くなった際には保険が適用されて銀行への返済は無くなるので、返済の無いマンションが残された家族に相続されて、生活費として毎月家賃を入金されます。家族の生活を保障するということだけではなく、家族に対して安心感を与えることにもなります。一般的な生命保険とは違い掛け捨てにはなりません。 団体信用保険の保障額は通常は1億円程度まで。銀行によっては外資と提携して3億円程度まで受ける場合もあります。銀行は団体信用保険に入ってない場合は「連帯保証人を付けて下さい。」と言って来ます。その場合は「団体信用保険に入る予定。」と連帯保証人なしで契約する事も可能です。ただし団体信用保険は個人で加入するものなので、法人で物件を購入する場合は加入できません。フルローンを組む銀行等は不動産への融資を個人名義しか取り扱っていないところもあります。 不動産投資が少ない自己資金で家族に財産を残せる優れた投資と言われるのはこれもその一つです。結婚を機に、子供が生まれたのが機に不動産投資を始めるのは家族を思っての事でもあるのです。 セミナーで私が話している事を主にアップしてきます。宜しくお願いします。 (酒本 経営戦略塾)
Read More »不動産投資戦略 その2
レバレッジをかける レバレッジという言葉をご存じでしょうか? レバレッジとはテコの原理のように、少ない力で大きな物を持ち上げることを意味します。不動産投資の世界や株・FXではこの言葉が頻繁に登場します。投資の世界でのレバレッジの意味は融資の力を借り最低限の自己資金で大きな金額を動かすことです。不動産投資は銀行の融資で不動産の購入や経営ができるわけですから、これほどレバレッジの効く投資はありません。 株式は信用取引が3倍、FXは25倍と法律で決まっておりますが、不動産においてはフルローンが組めるためにこれ限りではありません。不動産投資の最大の魅力は銀行融資を元にフルローンで投資できるという点です。日銀のマイナス金利政策にて貸出金利も低く比較的少ない自己資金での購入が可能となり、スルガ銀行など銀行によってはフルローンが組める時代になりました。1棟あたりに充当する自己資金を抑える事により短期間で棟数を増やす事も可能となります。銀行が融資のハードルを下げてる今は不動産投資は一種の時流やタイミングであると言えます。 政府が日銀の政策を変えれば米国大統領が変わって政策が180度変わるものもあるので、そうなると現在の様な不動産投資ブームのチャンスは逃す事になります。現在が不動産投資のいい時期であると言えます。 最初に不動産投資としてまず頭に浮かぶのは区分マンションと思います。区分マンションは価格も手頃でリスクも少ないというイメージがあるかも知れませんが、空室になった途端に収入がゼロになってしまいそれどころか管理費、修繕積立金、金利返済の支払いのみが残る形となります。1棟買いの場合では8割の入居でも収入がゼロになるという事は無く、また家賃の操作により安定したインカムゲインを得る事が出来ます。インカムゲインは全体家賃×入居率で調整が効くわけです。 同じ不動産の融資でもマイホームと不動産投資では性格がまったく異なります。マイホームというのは資産と思われがちですが、ロバート・キヨサキの「金持ち父さん・貧乏父さん」の本にある様に利益を生むものを「資産」と捉えるならば、前者は利益を生まず消費するだけ、不動産投資はインカムゲインとキャピタルゲインを得られる「資産」となります。 またマイホームは個人の信用力・収入が審査の軸となりますが、不動産投資は個人の信用力よりも物件そのものを担保とする為、物件のインカムゲイン(家賃)の事業計画書が審査の軸となります。不動産投資はまずこの根本を理解しておく必要があります。 ではどの銀行で融資を受けるべきか? 地銀はメガバンクと比べて融資が通りやすいのです。さらに都市銀行と地銀を比較すると地銀の方が融資は通りやすいのです。自身に一定の700万円以上の収入と物件の利回りが高ければ1棟をフルローンで借りられることも可能です。地銀を利用する際の注意点は、対象物件・住居・勤務地などが営業エリア内にあることが前提となっている場合が多いので、地域の銀行はどこが良いかを吟味する必要があります。 (酒本 経営戦略塾)
Read More »賃貸併用住宅って、どうなの?
賃貸併用住宅って、最近目にするようになったけど、どうなの? 丸の内のJPタワーで、毎週賃貸併用住宅セミナーを開催している、ZWEISPACEさんに聞いてみました。 参加者は、住宅購入予定の方の他、一棟マンション保有者など、さまざま。一棟マンションを保有していても、賃貸併用住宅は魅力のようだ。f マンションとの比較 資産額の検討 負債額の検討 ローン金利、デュレーションの検討 など、検討する項目が、住宅ローンとは異なります。 まずは、セミナーにいってみては。
Read More »不動産管理会社の選び方(初級編)
不動産管理会社の選び方 平成29年1月31日 株式会社エムジェイエフ 代表取締役 森川 裕昭 一般に「マンションは管理を買え」とよく言われます。 実際にお住まいされる物件をお探しの場合、「管理の状況」は気になる所だと思います。「居住の快適性・生活の利便性」を第一に物件を選択されるでしょう。 不動産投資として購入される場合、オーナーは実際にお住まいになることがないため、物件の判断材料は、いかに収益が上げられるかを着目した「収益性」にて判断されることでしょう。 購入時に不動産会社から発行される「重要事項説明書」の中では、「管理の状況」に関して説明される内容は、月額管理費・修繕積立金額とその滞納の有無、修繕積立金総額、管理組合の負債の有無などの財政状況や、管理会社名やその連絡先、管理形態等の説明にとどまります。当然、その財政状況等は重要な物件の資料ではありますが、あくまで現在(過去)の状況を示したものとなります。 しかし将来においては、実際の管理状況、トラブルの有無やその対処履歴、今後の管理方針など「管理のあり方・管理のあるべき姿」が、物件としての資産価値を決定づけていきます。つまり、管理の質を向上させ高度に維持をしていけば、競合物件と比べて資産価値が保てることを意味しています。 この不動産投資として一番大事なことは、当然ながら、賃料収入を得ることです。どれ程物件の外観や設備等に投資をしようが、物件に対してオーナーに強い思い入れがあろうが、また、賃料等の値下げをしようが、実際入居希望者が数ある物件の中からその物件に住むことを選択して頂けなければ、このビジネスは成り立ちません。 多くの入居希望者は、あらかじめ初期費用や賃料等の負担額、立地、設備等の基本情報を不動産会社より提供してもらった上で、実際に現地を内覧し最終決定を行ないます。内覧する際に確実に利用する共用部分(エントランス・共用廊下・エレベータ等)の美観が保たれていなければ(清潔感がなければ)、また、掲示板等での警告貼紙等で、まるで犯人捜しをしているような、あるいは入居者間での責任の擦り付け合うような雰囲気がにじみ出ている物件なら、入居希望者はその物件を避けていくでしょう。つまり、管理をふくめた現場の状態そのものが意思決定の最終判断材料となり、それを不快に感じさせてしまったならば、その心象を覆すことは以後不可能に近くなります。 凡そ、単身者向け物件は平均4年、ファミリー向け物件であれは平均5年間、借りるというデータがありますが、その収益を逃す原因となります。 オーナーは、入居希望者や入居者目線で物件を管理していく必要があります。 その重要な使命をオーナーに成り代わって業務を行う不動産管理会社は、業務内容により、通常2つに分類できます。建物管理会社と賃貸管理会社です。 建物管理は、「共用部分の維持・管理するため、清掃・点検・修繕などの各種業務を行うこと、またはそれを請け負う事業」のことです。 主な業務として、①清掃・衛生管理(日常清掃)、②設備管理(給排水・電気・通信設備)、③常駐警備・防災(巡回)、④管理サービス(居住者への利便向上のためのサービス)、⑤管理組合の運営補助(出納業務・総会運営補助業務)等に分けられ、オーナー(管理組合)と管理会社との間で締結される「請負契約書」に基づき、業務を行っていきます。 実際の請負契約においては、物件の築年数・性質・規模等を踏まえ、その物件のあるべき姿を管理会社に説明し、綿密な打ち合わせのもとに、無駄なコストをかけないよう業務内容を決定することが必要です。また、随時、状況に応じて、契約内容業務頻度を変更することも必要だと言えます。 当然コストをかけるほど成果が上がることにつながりますが、その一方、収益が下がることも意味しますので、入居希望者・入居者がその物件に求める管理状態がどのレベルであるのかを見極めることが重要です。 特に日常清掃に関しては、作業者の能力・向上心・責任感により完成度が大きく変わります。日常清掃をシビアに行うことが清潔感を保てる一番の近道です。現場チェックを常に行い、些細なことでも管理会社に対し要望や指摘を行うことが重要となります。入居者側の協力も必要でしょう。オーナー自身もその管理サービスの一役を担うということを踏まえなければならないと思われます。 一方、賃貸管理は、「オーナーの代理として専有部分を使用・利用して、オーナーの収益を上げるために行う事業」のことです。 大きく分けて3つの業務に分かれます。①入居募集業務、②契約管理業務、③出納業務に大別されます。 入居募集業務(リーシング業務)は、自社にて入居希望者を直接探す場合と、他社仲介業者に対し情報提供を行うことで入居者を探してもらう場合があります。いずれの方法においても、オーナーは賃料収入として収益を得ることが最大の目的ですので、入居者集客能力が管理会社の能力であるといってもいいでしょう。 契約管理とは、オーナーの代理として、賃貸借契約管理業務(賃貸借契約内容に基づいた対応や業務)、現場管理業務(クレーム対応・メンテナンス対応・退去時原状回復工事)を行い、スムーズな賃貸経営を継続するために行います。 出納業務は、家賃等の集金および送金、未納者に対しては滞納督促を行い、キャッシュフロー面でオーナーの賃貸経営をフォローしていきます。 それぞれの業務内容は、オーナーと管理会社との間で締結される「管理委託契約書」に基づき、業務を行っていきます。建物管理と異なるのは、業務内容自体はどの会社も大差がなく、対応方法、責任範囲、期日、金額等に差異があると言えます。但し、担当者の能力・対応次第で全く違う結果になりかねないということです。特にクレーム対応は、対応によって入居者の理解が得られずいずれ退去していくきっかけとなりますので、注意が必要です。管理会社として、「テナントリテンション(入居者に永く住んでもらう為の満足度アップ対策)」は重要な対策です。入居者に長くお住まいいただくことが、最大の収益を得られることにつながります。 管理会社は、規模により特色があると言えます。 大規模管理会社は、長所としては、企業として安定と実績があげられます。一方短所としては、個性を排除されている(完全定型化・即座に対応できない、依頼者の意向が反映しづらい)、コストが比較的に高い、実務作業者の経験や能力は未知数であるなどのデメリットが考えられます。 小中規模管理会社は、長所としては、依頼者の意向が反映しやすく利益度返しでの対応がしやすく融通がきくこと、コストが比較的安価であることがあげられます。短所としては、企業として不安定で実績がない、将来性が不透明、作業者・指示者の経験や能力が欠如している可能性がある、時間と経費を十分掛けられないので成果が上がりづらい、物件所在地・物件種別・業務内容が限定されている、緊急時対応や今後のコンサルティングに対して提案できる選択肢が少ないことやその場合高額になりやすいなどが考えられます。 いずれも一長一短があり、大規模な管理会社のほうが安心であると思われがちですが、実際の担当者・作業者の能力・責任感により、成果が大きく変わることを認識しておくべきだと思います。 物件を取得するときに紐づきにて管理会社が決定していることも多いですが、担当者を含め管理会社の対応能力によりその後の物件の価値が決まってくるとも言えます。管理状態も物件価値の重要な要素であります。一度「管理が悪い」と世間に評価された物件を覆すには難題と言えます。 また、管理料等の報酬額も千差万別です。一概に安価な設定をしている管理会社であれば良いのではなく、例え報酬額が高くても、オーナーにそれ以上の収益をもたらせてくれる対応をして頂けるのであれば、その管理会社を選ぶことは正しいといえるのでないのでしょうか。 通常、管理会社の担当者は、月次をサイクルとしてルーチンワークで動いております。契約内容が多岐にわたる「賃貸借契約書」や「請負契約書」に基づいて、オーナーを代理して作業を行っております。電話応対、書類作成、運用システムの登録、各種書類の発送・回収・保管等に代表される単純作業に追われます。その中で、クレーム対応など突発的な緊急性がある業務が舞い込んできます。そのようなルーチンワークをこなす中で、緊急な対応を求められ続けます。 その多忙な時間の制約がある中で、担当者はオーナーに対して将来を見越した有効な改善や提案できる時間や機会が持てないのが通常です。ですが、オーナーの資産価値を上げることができるのは、物件の状況を把握できる資料を持ち、かつ専門知識を持った管理会社だけなのです。管理会社としてはルーチンワークの業務はこなせて当たり前の時代。オーナーに対し、より収益を上げるための改善・企画提案を行えているかどうかで、信頼できる管理会社であるかが選別できるのではないでしょうか。 時には、管理会社として収益を上げるために必要な追加投資をして頂くようオーナーにお願いすることがあるでしょう。担当者としては「追加投資をしてください」というのは気持ちが乗らない、嫌われるのではないかと恐れて言い出しにくい。また会社より売り上げを上げないといけないという指示も出ているかも知れません。ですが、オーナーの資産価値を上げるという使命を持った立場に立つのであれば、管理会社は、市場調査を正確に行い、その追加投資が収益性を向上するのに有効であるかを判断できる資料を提示することにより、最終判断をオーナーに仰ぐことが、重要な仕事であると思います。 それができる管理会社が今後選ばれていくのではないのでしょうか。
Read More »満室経営の秘訣
満室経営をされている不動産オーナーさんに お話しをきいていきます。 現在、準備中です。
Read More »東京の新築一棟アパート
東京の新築一棟アパートが注目されています。
Read More »